日本の道徳って
日本の道徳について。
丁度さっき、駅前を歩いていたら、スラブ系の女性に声をかけられた。どうやら、募金のお願いらしい。たどたどしく英語を交えると、僕の手はいつの間にか、彼女の手に500円玉を手渡していた。
募金をし終え、その場を立ち去った後に、さっきまでの一連の動作の自然さと不自然さにハッとさせられるものがあった。
刷り込まれたように、僕は募金を済ませた。実情を言ってしまえば、殆どは感情でなく、義務感でだ。「こういうケースにはこうするべきだ」、そういった経験則からの速やかな行動であった。
その流れは、おそらくとても自然だったと思う。
でも、ちょっと時間をおいて、よく考えたら、それがとても不自然だということに気がついてしまった。
なんで自分は、疑いもせず募金をしたんだろう。実は、「嫌です」と拒否する選択肢も存在していたというのに。あたかも、「募金するしかない」という現状であったかのように、僕はそれを正しいと判断し、実行していた。
そうした社会規範のようなものに完全に則って生きることが本当に「正しい」と言えるのだろうか?と僕は自問した。
そして、その判断のルーツが、僕が小学生の時に受けたであろう「道徳の授業」にあるのではないか、という所にまで思い至った。
そういった了見で、今回は自分が「日本の道徳」について自由に思ったことを書いていこうと思う。
あくまで、自分の意見なので、押し付けるつもりは無いことを、予め断っておく。
さて、始めたい。
長くなるかもしれないから、まず初めに「日本の道徳」について、自分の伝えたい第一のメッセージを「イメージ」としてまとめておく。
僕は「日本の道徳」に対する、独特なイメージを持っている。

日本の道徳は、“”自動販売機で売ってる味噌汁 “”みたいな感じだ。
…よくわからないと思うから、詳しく説明したい。
触れようと思えば触れられる環境がそこら中にあるのにも関わらず、わざわざ人様の手で人工的に「道徳」要素を作ってそれを学んでいる。
「道徳の教科書」がそれに当たる。
人工的に作った味っていうのは、味噌汁にしたって、なんだかぎこちない。
人の手で頑張って、出来るだけ自然に作ろうとしたものなんだろうけど。
それでもやっぱり、「自然になるように作ろう」とさえ思わず、本当の意味で「自然に」やったものしか本物にはなれない。
それが、母さんの作った味噌汁と、自動販売機で売ってる味噌汁の違いだ。
これが、僕からすれば、「道徳」にも同じことが言えてしまう。
子供が、日常生活の中で、友達と喧嘩して、「仲直りが必要だ」って経験から学ぶこと。
それと、道徳の教科書で偉い大人が「仲直りは必要だ」って巧妙な物語を使って子供に押し付けるのとではえらい違いだ。
教科書は、子供に経験を与えてくれない。だから、本物の感情っていうものも与えてくれない。
せいぜい子供に与えてくれるのは、「世の中はそういうことを求めてるのか」っていう「理解」であって、「感情」ではない。主体が自分ではないのだから、「感情」があったとしても、それは「同情」だし、学べるとしても、「社会」の常識だけ。
言い換えれば、社会のルールの「知識」だけだ。
自分の頭で、経験を体得することは出来ない。そこに本物の「教訓」はない。
自分が何を思ったかじゃない。道徳の授業なんて、「この物語を読んで、思ったことを自由に書きなさい」とか言ったって、結局は狙ってる感想の定型文に近づくように授業を組み立ててる。
こぶとりじいさんのお話で、「正直じいさんはハッピーエンドで、意地悪じいさんはバットエンド。同じじいさんなのに、正直じいさんだけが報われるのはおかしい!」なんていう感想を持ったら、おかしく思われるのが、道徳の授業の現状だ。
この話を用いることで、社会は「日頃の行いが良いものは救われて、悪いものは懲らしめられる」という、勧善懲悪の精神を子供に刷り込むことが可能だ。
なんだか、こうやって、考え方を揃えようとするのは、僕は嫌いだ。
長くなってしまったので、長文を読むのが苦手な方の為に、ここで総括するとすれば、僕が道徳の授業に言いたいことはこの二つだ。
「本物の道徳は教科書にはない!」
「教科書で考え方を揃えようとするのはやめて欲しい!」
以上だ。
短編小説「きをてらう」
僕の名前は寺煎 訊(てらい じん)。
でもそんなことはどうでもいい。
どうしてだ?
若い内は「衒う」べきだと思うんだけどなぁ。
だって、「衒」って字の意味は、
『才能を顕示すること』
『力を見せつけること』
それいつも皆やってるじゃないか。
学校のテストだって、大会だって、全部自己主張甚だしい『衒』なんだよ。
じゃあなんで『奇』は『衒』わない?
平凡な日常に飽き飽きしないのか?
私は「奇を衒う」ことに趣を感じる。
事を好む、人間だ。
「奇を衒わない」ことに楽しみはない。
皆、奇を衒おうよ!
日常にスパイスを!!
日々刺激を求めていこうよ!!!
常識…。
迷惑をかけなければそれが常識か?
常識なんて、変えれるのに…。
何故だ??
何故なんだ??
何故、君は家の中で傘をささない?
何故、君はノートを逆から使わない?
何故、君は名前を本名で書く?
何故、お守りは大切にとっておく?
何故、蛍光色は光る?
何故、夜になると眠くなる?
何故、僕は足が二本ある?
何故、僕は今すぐ走り出さない?
何故、僕はここにいる?
何故????
何故??君はあの時アイツを止めなかった??
それが普通じゃないからか?
普通じゃないもの、を見るために、僕達は普通を日々演じてるんだ。
「奇を衒わ」なきゃ、世界は進まない。
のに、
まるでら「奇を衒わない」ことを生きがいみたいに毎日君は生きてる。
何故??
何故だ???
どうしてみんなは奇を衒わない?
そして僕だけ衒うんだ?
どうしてなんだ???
どうしてだ?
どうしてだ……
どうして僕は、みんなと違うんだ?
――――――――――――――――
「きをてらう」 〜終〜
今日書いた二つの小説についてとこのブログについて
今日は二つの短編小説を書いた。
コンテストに応募するわけでもなく、ただこうしてブログに小説を書いてみたのは、レスポンスが欲しかったというのもあるけれど
文章を即席で書く練習のようなものに近い。
ブログは改行も簡単だし、スマホのフリックは割と早く入力出来る。
思ったよりはやく、千文字とか、二千文字とか、普通に到達した。
一つ目の「Neon」は、わりとフィクションで、名前を考えるのに少し時間をかけたかもしれない。
内容とあまりかぶらないが、タイトルはオシャレにしたかったから、そうした。
二作目の
「こころ」ころころ、ろここちゃん
は、題名こそだいぶ前に思いついていたものの、内容は即席で大体適当に作った。
夏目漱石の「こころ」をネタとして題材にしながら(最初は、言うまでもないと思ったが、あえて文字にしてネタとして消化していくことでユーモアが出ると思い、そうした。)
世の中のコロコロ移り変わる感じを皮肉に表現したかった。
多少、いや、結構、サイコ要素入ったけれども。
書いてて楽しかったし、また色々な分野に挑戦して書いていこうと思う。
ひとつ思ったのは、やはり短編小説とはいえども、長くなってしまっているのかも、ということだ。
だいたいブログだし、読みやすいように、千文字くらいを目安にしたい。
目安としては、今、この文でこのブログが始まって566字くらいだ。
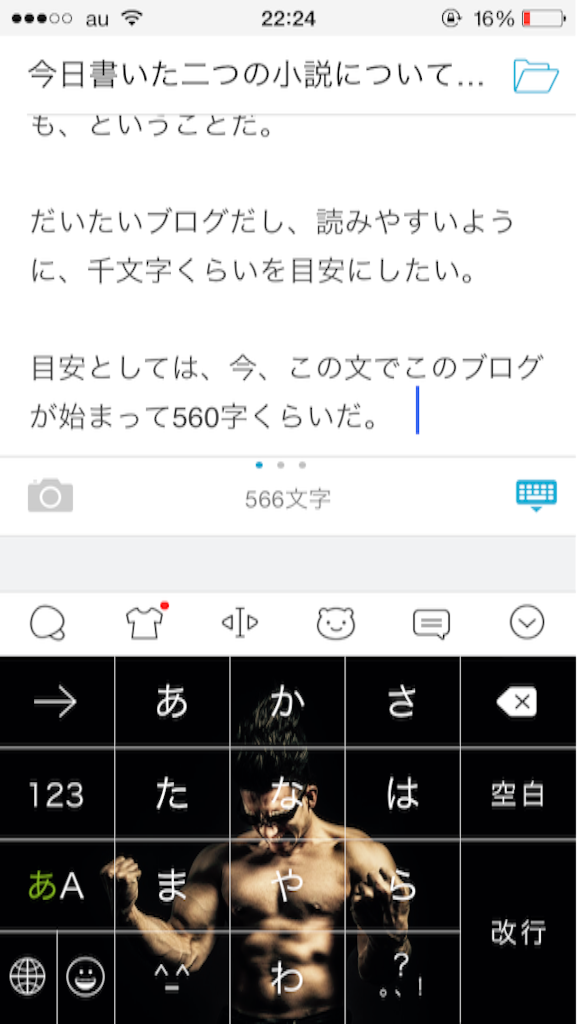
写真には660と文章に書いてしまってある。
しかし、ブログというのは書きながら過去の文に遡りすぐに訂正できるのが便利である。
それが投稿した後だとしても。

うーん、これ、なんかまた新しいテーマになるかな…?(笑)
とにかく、日々テーマを見つけて、小説にして書きたいと思います。
今でこそ、このブログのタイトルは「日記」になっているけど、ある意味日記ということでもあるかもしれない。
あと、タイトルはまた変えるかもしれない。
過去の、といっても幼い頃と故障できる時代の、自分のストーリーを見ると、
となりの森にいくと、木と木がおしゃべりしてたり、
サンタが誘拐されてそれを助けに行く5人?の物語とか
わりと面白いけどサイコ要素ある(笑)
なにこれ?って感じのところも多いけど、現在の俺の手でオマージュしたら面白いかな、っとも思いました。
それでは今日はこのへんで。
最後にもう一つほんとに短めの小説を書いて終わりにしよう。
どうなるんだろう。
テーマは「衒う」。
それでは。
短編小説「こころ」ころころ、ろここちゃん
私の名は神林ロココ。本名である。
親が考えて考えて考えて考えて、
この名前を付けてくれた。
世間は私のことを、俗に「DQNネーム」、と呼ぶ。
価値観を押し付けるな。
私は私の意思でこの名前を肯定しているのだから問題なかろう。
親が価値観を押し付けているのではない。
価値観を押し付けている、という価値観に押し付けられて私は生きている。
隣にはKという友人がいる。
勿論、夏目漱石の小説「こころ」に登場するKのようにイニシャルで呼称されているわけではない。
K、という本名なのだ。
倉本K、それが彼女の本名である。
私達が産まれる数年前、世の中には
「ネームブーム」が巻き起こった。
他にはない名前、自分の子供だけの価値観、特殊な生き方、それらを求めた親達は、自分の子供に変わった名前ばかりをつけ続けた。
結果、世の中は変わった名前だらけの世の中になった。
むしろ、普通の名前の方が珍しいくらいだ。
「珍しい」とは一体なんだったのか。
しかし、私もKも、自分の名前を恥じたことは一度もない。
現代は、アートやデザインを求める運動が急速に加速し、それぞれの価値観を過大とも思えるほどに尊重する世の中として出来上がってきている。
だから、芸術的観点からすれば、私の名前「ロココ」も「K」も、なんだか少しアーティスティックで素敵に感じられるのだ。
そういう感性なのだ。
そういう感性として完成されたのだ。
一昔前の概念なんてもう影と形もない。
一旦影を落とした時代はもう。
勢力を取り戻さない。
世の中なんてコロコロ変わる。
世の中なんて、コロコロ変わる。
それが最近の私の、世の中に対する印象である。
――――――――――――――――
Kと私の関係にも、同じようなことが言える。
Kと私は、今でこそ、こうやって、ミスタードーナツで席を並べて歓談する仲に落ち着いて入るものの、数ヶ月前までは、お互いを血で血を洗う戦友の仲、否、殺し合いの仲だった。
敬遠の仲、
否、犬猿の仲、否、虎龍の仲??
上手く例えが見つからない。
しかし、確かに言えるのは、お互いが被害者であり、加害者であり、
オブラートに包むことなく正確に言うなら、
殺人未遂者であり、被殺人者未遂であった。
しかし、そこには私とK以外に、もう一人の存在があった。
それが三条 燦(あき)である。
単純にいえば、私とKと燦の三人による、クラスの覇権の争いあいだった。
中学生のクラスの覇権争いほど恐ろしいことは無い。
被害をどのように敵に与えるか、それを自由に考えて、突拍子もなく実行する。
突飛で、沸騰的で、計画性が乏しいのだから、なおさら恐ろしい。
後先考えず、将来を顧みず、「殺人」なんていう手段を思いついて実行しようとするのだから、比喩ではなく、死ぬほど恐ろしい。
私とKは、その中でも特別に仲が悪かった。
しかし、戦場の仲で、そのいがみ合いは五十歩百歩のようなものだ。
私は、Kにも、燦にも、だいたい同じように百手を尽くしてあらゆる面で攻撃を行ってきた。そこに怠りや容赦はなかった。
この三国志は長くにわたって続くかと思われた。
しかし、ある日の晩。
燦は自殺して死んでしまったのだ。
思い返してみれば、あの日の前夜、私がいつもと違う方向に枕を置いていたのもなにかの因果かもしれない。
燦の机には遺書が遺されていたらしい。
簡単に言うと、
「私は将来、このままだと到底生きていくことが出来ないのだろうから、ここで死ぬ。」とのことだった。
どうしてもっと早く死ぬことが出来なかった、とか、遺体の処理の方法までは、流石に「こころ」のKのようには書いていてくれなかった。
流石にまだ中学生なのだから、そこまで考えることが出来なかったのは自然と考えるのが妥当だろう。
流石に考えて考えてあの文書を遺したのだったら、私も私としてがっかりだ。
私も、Kも、そこまで気に病むわけでは無かった。
もともと、ストレスに弱い体質ではない。
だからこそ、ここまで虐め合い、というか、クラス戦争を続けることが出来たのだった。
私達が殺したという説も持ち上がったが、すぐにそれは否定された。
学校側は社会的に「いじめ」より「自殺」として、処理したかったらしく、その通りに社会は動いた。
全く都合のいい社会だ。
それに、決め手となったのは、燦の遺書だ。あそこには、私達が殺した、もしくは、虐めた、という事実は一切書かれていなかった。物的証拠も何も無い。
あの遺書には「社会的に私達を抹殺する」ことすら書いてなかった。彼女の死について、その事実だけが私達にとっては大事だった。
「社会的」ということがこの場合、結構重要だったからである。
私達のクラスの覇権争いは、念に念を入れた形で、水面下で滔々と進行していた。
社会的にまずい場所には漏れていない。
そして、お互いに一滴も戦争の匂いを漏らさないことを暗黙の了解としていた。
だから、燦が死んだ後も、私とKの間に、戦争をやめざるを得ない、という状況は何も無かった。
けれど、私達は、戦争をやめた。
興醒めしたのだ。
なんだか、敵も自殺してしまったし、お互い半分半分くらいにクラスを支配しようか。
そんな流れになった。
別に、魔王に世界を半分やる、とかそういう上から目線の交渉をどちらかが持ちかけたわけでもなくて、
なんだか、自然と、そうなった。
そうなってからは、翌日から。
まるで昨日までのことが嘘のように私達は仲良しになった。
これが時の流れというものなのだ。
私はその時悟った。
こういう一日一日の変化が、積み重なって、積み重なって
それはもう積分みたいに積み重なって、時代の変化はいつの間にか、
気づかぬ間に、
私達に、訪れていて、
私達を、変えているんだろうなぁ。
その時、そう感じた。
率直に。愚直かもしれないが、純粋に。
ただはっきりと。
まるで悟ったかのような心境だった。
否
悟ったのだ。
人のこころって、こんなに移り変わりやすいんだ。よく勉強になった。
そう過去のことを考察しながら、
オールドファッションをほおばる。
Kは、ゆったりとコーヒーを口に運ぶ。
あの時の、Kに対する殺意、怨恨、ライバル心、葛藤、警戒、不安、怒り、
それらはもうどこにもぶつけようがない。
今でこそ、親友だ。
しかし、元は敵だ。
昨日の敵は今日の友。
これもまた都合のいい言葉だ。
まるで社会みたい。
もし私が、今彼女に殺意を抱いても、それはそれで「時代の流れ」なのだろうか?
今、目の前で、Kに、突然目潰しをしかけたら、一体どうなるんだろう。
これも、コロコロ変わる、こころの一環なのだろうか?
コロコロこころ、こころコロコロ。
殺、殺、こころ。こころ殺、殺。
「時の流れ」だから、多分許されるよね。
――――――――――――――――
「こころ」ころころ、ろここちゃん
〜終〜
短編小説「Neon」
秋が運んでくるのは哀愁の風だけではない。
受験生の葛藤と、それぞれの進路だ。
高校三年生の夏葉は、登校しながらその坊主頭を悩ませていた。
夏葉という名前ではあるが、男である。
秋らしい晴天の中、夏葉はとぼとぼと歩く。
(志望理由書…なんて書こうか…)
高校では真面目に授業を受け、成績もそこそこにとっていた夏葉は、この時期「推薦入試」を受けることになったのだった。
夏葉が目指しているのは都会のZ大学。
一個上にいたあこがれの先輩の春樹先輩が進学した有名大学だ。
まさか自分が推薦入試を受けられるとは思っていなかったが、嬉しさ反面不安が押し寄せる夏葉であった。
そこで学びたいことは何なのか?
具体的な指針は?目標は?
今までやってきたこと…
俺は何をしてきたのだろうか?
そんなことを考えているうちに、1日が終わろうとしていた。
最後のチャイムがなる。
今日は水曜日。
志望理由書の提出は今週の金曜が締切だ。
どうしようか…。
部活も引退した夏葉は、帰り道をとぼとぼと歩き始めた。
友達がセブンイレブンのおでんを激押ししていたことを思い出した。
そうだ、おでんでも食べていこう。
期待通り、セブンのおでんは今まで食べた他のコンビニのおでんよりも美味しかった。
一息ついた夏葉は、また悩み始める。
しかし、心に余裕が出来たのか、
春樹先輩に連絡してみようという手段を思いついたのだった。
(電話して、アドバイスをもらおう、なんでもいい。なんでもいいんだ…。)
電話をかけると、春樹先輩はすぐに電話に応じた。。
――――――――――――――――
「もしもし?」
「おっ、もしもし?夏葉か?」
「そうです!お久しぶりです!実は相談があってお電話を…
先輩はZ大学にどうやって入りましたか?」
「どうって…(笑)
普通に、一般入試だけど?」
春樹はなんだか居場所のない情けなさを感じた。
「実は…僕もZ大学を受けようと思っていて…。推薦ですけど。」
「おお!そうなのか!!
ほいじゃ、がんばれよ!!!」
「いや…、すいません。。
それで、少し、アドバイスをもらいたく…。」
「え?(笑)アドバイス?
俺、受けたことねぇけど(笑)」
なんだか夏葉は失敗しているパラレルワールドにいるような気分になった。
「すいません…。でも少し、Z大学についての情報とか、もらいたいなぁ…と思って。。」
だんだんか細くなっていく夏葉の声。
それを察したのか、先輩の春樹は少し考える。
「…。そうか。じゃあアドバイスしてやるよ。まず、今何に困ってる?
よく聞いててやるからよ。」
「え、っと…。志望理由書に書く内容が思いつかなくて、どうすればいいのかなって…。」
「そうか…。それならまず、具体的なテーマを決めるんだ。大学入って、学んで、それを活かして将来やりたいこと。
それに一貫してるテーマを見つけるんだ。」
夏葉は、ふと、昔老人ホームでボランティアをやっていた時のことを思い出した。
あの時、おじいちゃんおばあちゃんは、自分の一挙一動に感謝してくれて、笑ってくれた。それが夏葉にとっては忘れられない体験だった。
「そうですね…。高齢者の支援と、その為に福祉のことを学んで、若者と高齢者の距離を縮めていける企画をどんどん考えていきたいです。
それで、おじいちゃんおばあちゃんが元気になればなぁ…って。」
「いいじゃん!!!それ!!!お前の目指す学部に合ってるし!!!じゃあそれの具体的な目標を設定しなきゃな。」
「具体的な目標…というと?」
「高齢化社会の中で、自分の働きで地域の高齢者をどれだけ、どんな方法で楽しませられるか、支援できるかを、なんか…こう…方法として示すんだよ!」
先輩からアドバイスされればされるほど、なんだか自分が言っていることが大きいことのように思えてきた。
本当に自分はできるのか。
「いやぁ…思いつかないです…汗」
夏葉は、またボランティアのことを思い出した。おじいちゃんおばあちゃんの為のお祭りで、俳句や盆栽などの文化的発表が主な祭りだった。
そこにいたおじいちゃん、おばあちゃんはなんだか輝いて見えた。
「生きがい」ってこういうことなんだろうな、と夏葉が思った瞬間だった。
でも、その時、祭りを運営していたのは、地域でも有名な仕切り屋のおじさん。
テキパキと祭りを運営して、進行していたあの姿が自分に務まるとはどうしても思えなかった。
夏葉は
「う〜ん…。」
と、具体的な案を思いついたのにも関わらず、自信がなくて言えない。
春樹は、部活の先輩だ。
夏葉のことは、一年生の時からよく見てきた。
面倒見がよい春樹と、アドバイスにも「はい!」と従順に従う夏葉は、
まさに先輩と後輩を絵にしたような関係だった。
そんな夏葉の様子を、春樹は自然と察したのだった。
「夏葉…。なんだか悩んでいるようだけど、ひとつ言わせてもらうぞ。」
「はい。…なんでしょうか?」
「お前がな、如何に悩んでいようとも、俺は味方だ。口に出してみろ!」
春樹は銘々とした口調でそう告げた。
夏葉は、先輩に世話を見てもらっていた今までのことを思い出す。
先輩は、ぶっきらぼうで、大雑把なところもあるけれど、アイデアや、アドバイスはいつも的確だった。
夏葉は、改めて春樹を信頼して、言う。
「はい。実は、アイデアがあって。……えっと。。おじいちゃんおばあちゃんの為のお祭りを開くんです。文化的発表を主にした。それを仕切って、高齢者の生きがいのある場所を作っていきたいんです!!
しかし夏葉は依然として不安げだ。
…でも、自分に仕切り役が務まるかどうか…。やってはみたいんですけど。」
…春樹は決まっていたセリフを吐き出すかのように告げる。
「心配すんな!!!」
「…!!」
「出来るか出来ないかじゃねぇ!
とにかく志望理由書に書いてみろ!
今は嘘めいたことなのかもしれねぇが、
その思いがいつか芽生えて形になる日がきっとくる!だから心配するな!
最初は嘘かも知んねぇが、いつか本当になることだって、よくあるんだぜ。
とにかくそれを書くか、書かないか、だ。
出来るか出来ないかの問題じゃねぇ。
書くべきだ。いや書け!」
頭をガーンと打ち付けられたような衝撃が夏葉を貫いた。
これ以上ないアドバイスだった。
夏葉の思いは、春樹のアドバイスによってガチガチに塗り固められた。
もう、夏葉に迷いはない。
そして、不安も吹き飛んでいた。
「はい!先輩!!!!
やってみます!!先輩のおかげで志望理由書が書けそうです!!!明後日までだったんで、本当に危なかったです…(笑)」
「え??(笑)危な!!!(笑)
そりゃ良かったわ。頑張れよ!」
ガチャ。ツー、ツー、ツー、ツー。
――――――――――――――――
なんだか切る時はあっさりした人だなぁ。
夏葉は思った。
しかし、いつまでも頼れる先輩だなぁ、とつくづく感心した。
セブンを通り過ぎて、駅に向かう。
目の前の大きなビルの「カラオケ」の文字がネオン色に輝いていた。
光り輝くネオンはうっすらと光を弱めていった。
時計を見たら、電車の発車時刻まで、もう、あまり時間が無い。
夕暮れに染まる街並みに、夏葉は勢いよく駆け出していった。
「Neon」 ~終~